『闘う文豪とナチス・ドイツ:トーマス・マンの亡命日記』の悲哀 ― 2020年04月05日
『短篇小説講義』(筒井康隆)再読の準備として読んだ海外の古典短篇の中で、特に面白さがわからなかったのがトーマス・マンの『幻滅』だった。筒井氏の講義で、この天才作家の「若書き」短篇の魅力を知り、トーマス・マンという作家への多少の興味がわいた。それを機に次の新書を読んだ。
『闘う文豪とナチス・ドイツ:トーマス・マンの亡命日記』(池内紀/中公新書)
池内紀氏の著作はこれまでに『ヒトラーの時代』や『カフカの生涯』を面白く読んだ。だが、トーマス・マンにはあまり関心がなく、本書を敬遠していた。
私たち団塊世代が高校生の頃のスター作家だった北杜夫がトーマス・マンをやたら持ち上げていたので、いずれ読まねばならない高名な作家だとは意識していた。『トーニオ・クレーガ』だけは中学か高校のときに読んだが、無理に読了した記憶があるだけで感銘は受けなかった。この作家の肖像写真からは、堅苦しそうな取っつきにくい印象を受けた。
そんな状態で『闘う文豪とナチス・ドイツ』を読んだ。昔いだいたトーマス・マンのイメージはほとんど変わらなかったが、本書はとても面白い。トーマス・マンが残した1933年(58歳)から1955年(80歳)の日記からナチス関連の記述を抽出して解説している。世界情勢が投影された大作家の亡命生活の様子が目に浮かんでくる。
1929年に54歳でノーベル文学賞を受賞した高名な作家トーマス・マンは、1933年に発足したナチス政権には批判的で、1933年の国外講演の際に帰国を断念して亡命生活に入る。亡命生活の始まりからの日記は本人の意思で死後20年間は封印され、1975年に開封されたそうだ。
本書を読むとドイツからの亡命者社会の微妙な人間関係の様子がわかる。日記にはレマルク、ブレヒト、ツヴァイクなどへの言及はあるが、必ずしも好意的なものではない。当然ながら亡命というだけで一枚岩になるわけでなく、それでも亡命者であるという点に悲哀を感じる。
大作家トーマス・マンが「いじましいほどに世評を気にする人」で、写真を撮られるのが好きな「正装の人」だったという指摘も面白い。人並み以上に文才のあった長男が「偉大な男は息子などもつべきでない」というメモを残して自殺する話は哀れだが小説のようでもある。ナチスを逃れてアメリカに亡命したのに、戦後はマッカーシー旋風でスイスへ亡命するという運命は歴史を背負っている。
私が面白く思ったのは、晩年のトーマス・マンがカフカを読むシーンである。池上紀氏は次のように記述している。
「五十年余のキャリアをもつノーベル賞作家は不審でならない。自分とは何がどうちがうのか。もしこの異質の作家が「現代」ならば、自分は同じ位置にいることはできず、すでに終わった過去の作家に甘んじるしかないではないか。つねに「正装」を崩さなかった誇り高い人に、そのような屈辱が堪えられようか。」
カフカはトーマス・マンより8歳年下だが、ヒトラー台頭以前に40歳で亡くなり、死後に作品が世に出る。20世紀が進むとカフカの評価は高まりトーマス・マンはあまり読まれなくなる。私もカフカは読むが、トーマス・マンは敬遠する。
『闘う文豪とナチス・ドイツ:トーマス・マンの亡命日記』(池内紀/中公新書)
池内紀氏の著作はこれまでに『ヒトラーの時代』や『カフカの生涯』を面白く読んだ。だが、トーマス・マンにはあまり関心がなく、本書を敬遠していた。
私たち団塊世代が高校生の頃のスター作家だった北杜夫がトーマス・マンをやたら持ち上げていたので、いずれ読まねばならない高名な作家だとは意識していた。『トーニオ・クレーガ』だけは中学か高校のときに読んだが、無理に読了した記憶があるだけで感銘は受けなかった。この作家の肖像写真からは、堅苦しそうな取っつきにくい印象を受けた。
そんな状態で『闘う文豪とナチス・ドイツ』を読んだ。昔いだいたトーマス・マンのイメージはほとんど変わらなかったが、本書はとても面白い。トーマス・マンが残した1933年(58歳)から1955年(80歳)の日記からナチス関連の記述を抽出して解説している。世界情勢が投影された大作家の亡命生活の様子が目に浮かんでくる。
1929年に54歳でノーベル文学賞を受賞した高名な作家トーマス・マンは、1933年に発足したナチス政権には批判的で、1933年の国外講演の際に帰国を断念して亡命生活に入る。亡命生活の始まりからの日記は本人の意思で死後20年間は封印され、1975年に開封されたそうだ。
本書を読むとドイツからの亡命者社会の微妙な人間関係の様子がわかる。日記にはレマルク、ブレヒト、ツヴァイクなどへの言及はあるが、必ずしも好意的なものではない。当然ながら亡命というだけで一枚岩になるわけでなく、それでも亡命者であるという点に悲哀を感じる。
大作家トーマス・マンが「いじましいほどに世評を気にする人」で、写真を撮られるのが好きな「正装の人」だったという指摘も面白い。人並み以上に文才のあった長男が「偉大な男は息子などもつべきでない」というメモを残して自殺する話は哀れだが小説のようでもある。ナチスを逃れてアメリカに亡命したのに、戦後はマッカーシー旋風でスイスへ亡命するという運命は歴史を背負っている。
私が面白く思ったのは、晩年のトーマス・マンがカフカを読むシーンである。池上紀氏は次のように記述している。
「五十年余のキャリアをもつノーベル賞作家は不審でならない。自分とは何がどうちがうのか。もしこの異質の作家が「現代」ならば、自分は同じ位置にいることはできず、すでに終わった過去の作家に甘んじるしかないではないか。つねに「正装」を崩さなかった誇り高い人に、そのような屈辱が堪えられようか。」
カフカはトーマス・マンより8歳年下だが、ヒトラー台頭以前に40歳で亡くなり、死後に作品が世に出る。20世紀が進むとカフカの評価は高まりトーマス・マンはあまり読まれなくなる。私もカフカは読むが、トーマス・マンは敬遠する。
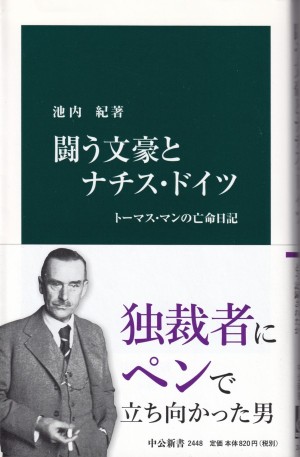
最近のコメント