地球儀を脇に『遊牧民から見た世界史』(杉山正明)を読んだ ― 2019年04月02日
『馬の世界史』(本村凌二)を読んで騎馬遊牧民の歴史への関心がわき、杉山正明氏の『遊牧民から見た世界史』を読んだ。
『遊牧民から見た世界史〔増補版〕』(杉山正明/日経ビジネス人文庫)
杉山正明氏の本を読むのは『クビライの挑戦』(講談社学術文庫)に次いで2冊目である。『クビライの挑戦』はモンゴル帝国の正当な評価を求める気迫に満ちた本だったが、本書はそれ以上に著者の熱気が伝わってくる。西欧的「文明主義」に疑念を呈し、遊牧民によってこそ「世界史」がかたち作られてきたと説く歯ごたえのある歴史書だった。
本書の扱う地域は広く、時間は長い。
舞台はアフロ・ユーラシア(ユーラシア+北アフリカ)である。この広大な地域は二次元の地図より地球儀の方が把握しやすいい。私は本書の地誌説明部分を地球儀を脇に置いて読んだ。遊牧民気分で中央アジアあたりから地球儀を眺めれば中国、インド、イランは近所でヨーロッパも遠くない。日本は極東、イギリスは極西だ。
遊牧民の歴史をヘロドトスが語るスキタイから書き起こし、司馬遷が語る匈奴に始まる紆余曲折を経て、クビライのモンゴル世界帝国までを語っている。スキタイの登場は紀元前6世紀末、モンゴルによるユーラシアの一体化は13世紀末だから、約1800年の時間を概観している。
本書を読むと、半世紀以上昔に高校世界史で習った中国史のイメージが大きく変わる。漢夷思想に呪縛された「正史」には歪みがあり、中国の歴史を作ってきた主役は多様な人々を抱え込んだ遊牧民の集団だったようだ。
本書を読んだ収穫は、「民族」という概念のあいまいさを確認できたことである。著者は冒頭で次のように述べている。
「現在、わたしたちが使っている民族、国家の概念は、たいへん強固で堅牢な語義とイメージをともなっている。それは、フランス革命を契機に、近代西欧でつくられた枠組み・価値観にもとづいている。ここ、200年のものである。」
古代ローマ関連の本を読むとフン族、ゲルマン、ガリア、ゴート、ヴァンダルをはじめ多くの蛮族が登場するが、それが民族なのか部族なの人種なのかつかみにくい。民族という概念はないと考えると少しすっきりする。
本書の末尾近くで著者は次のように述べている。
「本書が扱ってきたのは、人間というものの「かたまり」のかたちについてであった。では、人というものに、「まとまり」を与えるものはなにか。また、その「まとまり」には、どんなありかたがあるか――。(…)「国家」も「民族」も、歴史上の生成物である。変質・変成もするし、消長・生滅する。ただし、ほとんどの場合、「国家」が先にあって、「民族」はあとから成立した。はじめから、確固とした「民族」が存在し、「国家」はあとから出来たと考えるのは、おそらく誤りである。」
示唆に富んだ指摘である。「人間のかたまり」という融通無碍に思える概念が面白く、頭が柔軟になる気がする。
本書の元版は1997年刊行で、私の読んだ「増補版」は 2011年の刊行である。「増補版」のための追記で、著者は遊牧民への否定的イメージはこの十数年のうちに払拭されたと述べている。私が知らなかっただけで、近年、遊牧民の歴史研究進展によって見方がさま変わりしているようだ。
『遊牧民から見た世界史〔増補版〕』(杉山正明/日経ビジネス人文庫)
杉山正明氏の本を読むのは『クビライの挑戦』(講談社学術文庫)に次いで2冊目である。『クビライの挑戦』はモンゴル帝国の正当な評価を求める気迫に満ちた本だったが、本書はそれ以上に著者の熱気が伝わってくる。西欧的「文明主義」に疑念を呈し、遊牧民によってこそ「世界史」がかたち作られてきたと説く歯ごたえのある歴史書だった。
本書の扱う地域は広く、時間は長い。
舞台はアフロ・ユーラシア(ユーラシア+北アフリカ)である。この広大な地域は二次元の地図より地球儀の方が把握しやすいい。私は本書の地誌説明部分を地球儀を脇に置いて読んだ。遊牧民気分で中央アジアあたりから地球儀を眺めれば中国、インド、イランは近所でヨーロッパも遠くない。日本は極東、イギリスは極西だ。
遊牧民の歴史をヘロドトスが語るスキタイから書き起こし、司馬遷が語る匈奴に始まる紆余曲折を経て、クビライのモンゴル世界帝国までを語っている。スキタイの登場は紀元前6世紀末、モンゴルによるユーラシアの一体化は13世紀末だから、約1800年の時間を概観している。
本書を読むと、半世紀以上昔に高校世界史で習った中国史のイメージが大きく変わる。漢夷思想に呪縛された「正史」には歪みがあり、中国の歴史を作ってきた主役は多様な人々を抱え込んだ遊牧民の集団だったようだ。
本書を読んだ収穫は、「民族」という概念のあいまいさを確認できたことである。著者は冒頭で次のように述べている。
「現在、わたしたちが使っている民族、国家の概念は、たいへん強固で堅牢な語義とイメージをともなっている。それは、フランス革命を契機に、近代西欧でつくられた枠組み・価値観にもとづいている。ここ、200年のものである。」
古代ローマ関連の本を読むとフン族、ゲルマン、ガリア、ゴート、ヴァンダルをはじめ多くの蛮族が登場するが、それが民族なのか部族なの人種なのかつかみにくい。民族という概念はないと考えると少しすっきりする。
本書の末尾近くで著者は次のように述べている。
「本書が扱ってきたのは、人間というものの「かたまり」のかたちについてであった。では、人というものに、「まとまり」を与えるものはなにか。また、その「まとまり」には、どんなありかたがあるか――。(…)「国家」も「民族」も、歴史上の生成物である。変質・変成もするし、消長・生滅する。ただし、ほとんどの場合、「国家」が先にあって、「民族」はあとから成立した。はじめから、確固とした「民族」が存在し、「国家」はあとから出来たと考えるのは、おそらく誤りである。」
示唆に富んだ指摘である。「人間のかたまり」という融通無碍に思える概念が面白く、頭が柔軟になる気がする。
本書の元版は1997年刊行で、私の読んだ「増補版」は 2011年の刊行である。「増補版」のための追記で、著者は遊牧民への否定的イメージはこの十数年のうちに払拭されたと述べている。私が知らなかっただけで、近年、遊牧民の歴史研究進展によって見方がさま変わりしているようだ。
『モンゴル帝国と長いその後』の射程は現代に及んでいる ― 2019年04月07日
杉山正明氏の『遊牧民から見た世界史』に続いて同氏の次の本を読んだ。
『モンゴル帝国と長いその後』 (杉山正明/講談社学術文庫)
本書は約10年前に講談社が刊行した『興亡の世界史』という叢書を文庫化したものである。モンゴル帝国興亡の概説書ではなく、モンゴル帝国の世界への影響と世界史における位置づけを述べた本だった。チンギス・カンやクビライには簡単に触れているだけで、モンゴルとその周辺を視座にアフロ・ユーラシアの歴史を語っている。
巻末に本書の内容に対応した年表があり、それは「前2千年紀前半の古アッシリア時代」に始まり、「2001年のニューヨーク同時多発テロ、アメリカのアフガンへの軍事作戦開始」で終わっている。項目が多いのは13世紀から15世紀で、その時代が本書のメインではあるが、古代から現代まで射程に入っている。壮大である。
杉山氏の本を読むのは3冊目で、著者の考えや語りに少し慣れてきた。従来の世界史像は西欧視点や中国視点によって歪められた点が多いという指摘は、歴史をトータルに把握するうえで心すべきことだと納得できる。
本書によって、おぼろげながら『集史』という歴史書の概要を知ることができた。モンゴル帝国の立場からペルシア語で書かれた浩瀚な歴史書で、世界各国で170年を越えて研究されているが、いまだに十全な定本・定訳はないそうだ。杉山氏は次のように述べている。
「ヘロドトス『歴史』や司馬遷『史記』などの先行する“大歴史書”にくらべ、少なくともスケールの点では誰が見ても、はるかにそれを上回る『集史』についての言及の薄さは、世界の歴史学の片寄りを端的に示すものだろう。」
本書の終章のタイトルは「アフガニスタンからの眺望」で、「文明の十字路」とも呼ばれるアフガニスタンに集約された歴史と現状をふまえ、モンゴル後の世界史を概観している。アフガニスタンはバーミヤーン遺跡のある国で、1979年のソ連の侵攻以来、紛争が続いている。最近、たまたまある人から「外務省が渡航を禁止しているので、日本ではアフガニスタンの遺跡を研究する人がいなくなった」という話を聞いたばかりだったので、この終章を興味深く読んだ。
モンゴル帝国の「長いその後」は現代にまで及んでいる。杉山氏は、次のように述べている。
「ロシア・中国どちらも「帝国」的な大領域という巨大遺産とともに生きている。それも、長いスパンで見ればモンゴルの遺産なのかもしれない」
『モンゴル帝国と長いその後』 (杉山正明/講談社学術文庫)
本書は約10年前に講談社が刊行した『興亡の世界史』という叢書を文庫化したものである。モンゴル帝国興亡の概説書ではなく、モンゴル帝国の世界への影響と世界史における位置づけを述べた本だった。チンギス・カンやクビライには簡単に触れているだけで、モンゴルとその周辺を視座にアフロ・ユーラシアの歴史を語っている。
巻末に本書の内容に対応した年表があり、それは「前2千年紀前半の古アッシリア時代」に始まり、「2001年のニューヨーク同時多発テロ、アメリカのアフガンへの軍事作戦開始」で終わっている。項目が多いのは13世紀から15世紀で、その時代が本書のメインではあるが、古代から現代まで射程に入っている。壮大である。
杉山氏の本を読むのは3冊目で、著者の考えや語りに少し慣れてきた。従来の世界史像は西欧視点や中国視点によって歪められた点が多いという指摘は、歴史をトータルに把握するうえで心すべきことだと納得できる。
本書によって、おぼろげながら『集史』という歴史書の概要を知ることができた。モンゴル帝国の立場からペルシア語で書かれた浩瀚な歴史書で、世界各国で170年を越えて研究されているが、いまだに十全な定本・定訳はないそうだ。杉山氏は次のように述べている。
「ヘロドトス『歴史』や司馬遷『史記』などの先行する“大歴史書”にくらべ、少なくともスケールの点では誰が見ても、はるかにそれを上回る『集史』についての言及の薄さは、世界の歴史学の片寄りを端的に示すものだろう。」
本書の終章のタイトルは「アフガニスタンからの眺望」で、「文明の十字路」とも呼ばれるアフガニスタンに集約された歴史と現状をふまえ、モンゴル後の世界史を概観している。アフガニスタンはバーミヤーン遺跡のある国で、1979年のソ連の侵攻以来、紛争が続いている。最近、たまたまある人から「外務省が渡航を禁止しているので、日本ではアフガニスタンの遺跡を研究する人がいなくなった」という話を聞いたばかりだったので、この終章を興味深く読んだ。
モンゴル帝国の「長いその後」は現代にまで及んでいる。杉山氏は、次のように述べている。
「ロシア・中国どちらも「帝国」的な大領域という巨大遺産とともに生きている。それも、長いスパンで見ればモンゴルの遺産なのかもしれない」
『バクトリア王国の興亡』は研究者の考察と随想の書 ― 2019年04月14日
ちくま学芸文庫の近刊『バクトリア王国の興亡』を読んだ。
『バクトリア王国の興亡:ヘレニズムと仏教の交流の原点』(前田耕作/ちくま学芸文庫)
1992年に刊行された書の増補改訂版である。バクトリア王国とは紀元前3世紀末から紀元前2世紀なかばまで、アフガニスタン北部から北西インドのあたりに存在したギリシア系の国、つまりはヘレニズムの国である。私にほとんど未知の国だが、高校世界史には登場している。
本書を読もうと思ったのは、最近読んだ『モンゴル帝国と長いその後』 (杉山正明/講談社学術文庫)の終章で「文明の十字路・アフガニスタン」の波乱に満ちた歴史に接し、この機会にバクトリア王国について知見を得よう思ったからである。
そんな動機で読み始めたが、未知の地名・人名が頻出して私には難儀な本だった。地名は本書収録の地図や他の歴史地図で確認しながら読み進めた。人名も随時ネット検索などで調べたが不明の人も多い。
本書に出てくる人名は3種類に分けられる。まずは歴史上の登場人物である。これは「世界史人名辞典」、年表、家系図などで確認できる。次に歴史記述者で、ヘロドトス、プルタルコス、ポリュビオス、ストラボン、玄奘から史記・漢書に及ぶが、これら有名固有名詞は何とかなる。問題は3種類目の研究者・発掘者・探検家たちである。百年以上昔の人から現代人まで多様で、大半が私には未知の人物である。それでも頻出する人名に関しては多少のイメージができてきた。
本書はバクトリア王国の解説書ではない。古代の歴史家や劇作家が残した文書や発掘された遺物(古銭、碑文など)をベースに、これまでの研究者たちの見解の紹介・検討を交えてバクトリア王国興亡の姿を考察した書である。同時に古代の文明の交流と融合に思いを馳せる随想の書でもある。
本書によって、古代史研究における発掘の面白さと重要性をあらためて認識した。バクトリア王国に関する史書の記述は限定的で不明なことも多く、発掘された古銭の研究が史実確認の大きな手がかりになるそうだ。そして、かつてバクトリア王国があったと思われる地域の発掘は未だに終わっていない。1979年のソ連のアフガニスタン侵攻で発掘が中断され、政情の不安定は現代まで続いている。
アレクサンドロスが遠征先で見初めた妃ロクサネはバクトリア人で、セレウコスの妻もバクトリア人だった。本書はバクトリア王国成立以前のアレクサンドロスの遠征やその後継者たち(ディアドコイ)の争いにかなりのページを割いている。それがヘレニズム時代の始まりであり、インドにまでギリシア風の文化を伝えたバクトリア王国こそがヘレニズムのシンボル的存在だからだろう。
杉山正明氏は『モンゴル帝国と長いその後』において、アレクサンドロスの極端な英雄化やヘレニズムという歴史概念の強調は西欧文明中心の見方だと指摘していた。そういう観点をふまえて本書を読んだつもりだが、特に違和感はなかった。ギリシア、イラン、インドの文化が何等かの形で融合していったのは確かであり、人間の集団の交流によって融合が発生するのは自然なことだと思える。
読了するのに時間がかかった難儀な本だったが、予備知識を得たうえで味読したい本である。そうすれば著者の感慨を多少は共有できるかもしれない。
『バクトリア王国の興亡:ヘレニズムと仏教の交流の原点』(前田耕作/ちくま学芸文庫)
1992年に刊行された書の増補改訂版である。バクトリア王国とは紀元前3世紀末から紀元前2世紀なかばまで、アフガニスタン北部から北西インドのあたりに存在したギリシア系の国、つまりはヘレニズムの国である。私にほとんど未知の国だが、高校世界史には登場している。
本書を読もうと思ったのは、最近読んだ『モンゴル帝国と長いその後』 (杉山正明/講談社学術文庫)の終章で「文明の十字路・アフガニスタン」の波乱に満ちた歴史に接し、この機会にバクトリア王国について知見を得よう思ったからである。
そんな動機で読み始めたが、未知の地名・人名が頻出して私には難儀な本だった。地名は本書収録の地図や他の歴史地図で確認しながら読み進めた。人名も随時ネット検索などで調べたが不明の人も多い。
本書に出てくる人名は3種類に分けられる。まずは歴史上の登場人物である。これは「世界史人名辞典」、年表、家系図などで確認できる。次に歴史記述者で、ヘロドトス、プルタルコス、ポリュビオス、ストラボン、玄奘から史記・漢書に及ぶが、これら有名固有名詞は何とかなる。問題は3種類目の研究者・発掘者・探検家たちである。百年以上昔の人から現代人まで多様で、大半が私には未知の人物である。それでも頻出する人名に関しては多少のイメージができてきた。
本書はバクトリア王国の解説書ではない。古代の歴史家や劇作家が残した文書や発掘された遺物(古銭、碑文など)をベースに、これまでの研究者たちの見解の紹介・検討を交えてバクトリア王国興亡の姿を考察した書である。同時に古代の文明の交流と融合に思いを馳せる随想の書でもある。
本書によって、古代史研究における発掘の面白さと重要性をあらためて認識した。バクトリア王国に関する史書の記述は限定的で不明なことも多く、発掘された古銭の研究が史実確認の大きな手がかりになるそうだ。そして、かつてバクトリア王国があったと思われる地域の発掘は未だに終わっていない。1979年のソ連のアフガニスタン侵攻で発掘が中断され、政情の不安定は現代まで続いている。
アレクサンドロスが遠征先で見初めた妃ロクサネはバクトリア人で、セレウコスの妻もバクトリア人だった。本書はバクトリア王国成立以前のアレクサンドロスの遠征やその後継者たち(ディアドコイ)の争いにかなりのページを割いている。それがヘレニズム時代の始まりであり、インドにまでギリシア風の文化を伝えたバクトリア王国こそがヘレニズムのシンボル的存在だからだろう。
杉山正明氏は『モンゴル帝国と長いその後』において、アレクサンドロスの極端な英雄化やヘレニズムという歴史概念の強調は西欧文明中心の見方だと指摘していた。そういう観点をふまえて本書を読んだつもりだが、特に違和感はなかった。ギリシア、イラン、インドの文化が何等かの形で融合していったのは確かであり、人間の集団の交流によって融合が発生するのは自然なことだと思える。
読了するのに時間がかかった難儀な本だったが、予備知識を得たうえで味読したい本である。そうすれば著者の感慨を多少は共有できるかもしれない。
チェーホフの『かもめ』は謎が残る ― 2019年04月17日
新国立劇場小劇場でチェーホフの『かもめ』(演出:鈴木裕美)を観た。半世紀以上昔の学生時代、チェーホフの4大劇(『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』『桜の園』)の戯曲から大いなる感銘を受けた。だが、舞台は『桜の園』を観たことがあるだけで、『かもめ』の観劇は初体験である。
チェーホフの戯曲が印象深いのは確かだが、半世紀以上が経過するとその漠然たる印象の記憶だけが残っていて、芝居の内容はほとんど失念している。観劇前に書架の奥にあった新潮文庫の『かもめ・ワーニャ伯父さん』(神西清訳)を再読し、チェーホフ世界がよみがえった。
上演パンフによれば『かもめ』の翻訳は十数種あり、今回はあえて英語台本を日本語に翻訳したものを使ったそうだ。と言っても、原作を逸脱しているわけではなく、チェーホフ世界の雰囲気を堪能できた。
チェーホフを「暗い」という人がいるが、暗いとは思わない。苦さと滑稽が混ざった、チェーホフ的とか表現できない独特の味わいの世界だと思う。
『かもめ』はコンスタンティン(トレープレフ)という若者の自殺を医師ドールンが作家トリゴーリンに耳打ちする衝撃的で静かなシーンで幕切れになる。印象深い幕切れだが、謎が残る。
戯曲を読んでもよくわからず、舞台を観てさらに謎が深まったのは「かもめの剥製」である。シャムラーエフ(管理人)がトリゴーリン(作家)からの依頼でかもめを剥製にしたと言って、それを取り出すが、トリゴーリンは「覚えがないなあ」を繰り返す。
この芝居では「かもめ」は最初から象徴的に扱われている。ニーナの「私は――かもめ。そうじゃない。私は――女優」という科白も印象的である。だが、「かもめの剥製」は唐突で不思議である。その不気味さが解読できない。
トリゴーリンの記憶喪失か、シャムラーエフの悪意か、別のだれかが剥製作成を依頼したのか、また、剥製に含意されているのは否定的なものなか肯定的なものなのか、私にはわからない。生と死を定着させて後世に伝える「文学作品」の象徴なのだろうか。『かもめ』は名作古典なので、これまでにいろいろ解読されてきたのだろうとは思われるが…
チェーホフの戯曲が印象深いのは確かだが、半世紀以上が経過するとその漠然たる印象の記憶だけが残っていて、芝居の内容はほとんど失念している。観劇前に書架の奥にあった新潮文庫の『かもめ・ワーニャ伯父さん』(神西清訳)を再読し、チェーホフ世界がよみがえった。
上演パンフによれば『かもめ』の翻訳は十数種あり、今回はあえて英語台本を日本語に翻訳したものを使ったそうだ。と言っても、原作を逸脱しているわけではなく、チェーホフ世界の雰囲気を堪能できた。
チェーホフを「暗い」という人がいるが、暗いとは思わない。苦さと滑稽が混ざった、チェーホフ的とか表現できない独特の味わいの世界だと思う。
『かもめ』はコンスタンティン(トレープレフ)という若者の自殺を医師ドールンが作家トリゴーリンに耳打ちする衝撃的で静かなシーンで幕切れになる。印象深い幕切れだが、謎が残る。
戯曲を読んでもよくわからず、舞台を観てさらに謎が深まったのは「かもめの剥製」である。シャムラーエフ(管理人)がトリゴーリン(作家)からの依頼でかもめを剥製にしたと言って、それを取り出すが、トリゴーリンは「覚えがないなあ」を繰り返す。
この芝居では「かもめ」は最初から象徴的に扱われている。ニーナの「私は――かもめ。そうじゃない。私は――女優」という科白も印象的である。だが、「かもめの剥製」は唐突で不思議である。その不気味さが解読できない。
トリゴーリンの記憶喪失か、シャムラーエフの悪意か、別のだれかが剥製作成を依頼したのか、また、剥製に含意されているのは否定的なものなか肯定的なものなのか、私にはわからない。生と死を定着させて後世に伝える「文学作品」の象徴なのだろうか。『かもめ』は名作古典なので、これまでにいろいろ解読されてきたのだろうとは思われるが…
モンキー・パンチの訃報に接し昔の『ルパン三世』を読み返した ― 2019年04月19日
『ルパン三世』の原作漫画家モンキー・パンチが81歳で逝去した。4月18日の朝日新聞の「天声人語」も日経新聞の「春秋」も『ルパン三世』の作者を追悼する内容で、『ルパン三世』が国民的人気を博した作品・キャラクターだと認識した。
そんな記事を読んでいて、大昔に買った原作漫画がまだあるのではと思いあたり、本棚の奥を探索すると、1968年発行の『漫画アクション・コミックス』が出てきた。『漫画アクション』連載の『ルパン三世』のNo1からNo14までを収録した総集編である。
調べてみると『ルパン三世』は『漫画アクション』の創刊号(1967年8月10日号)から連載が始まっている。私の持っている総集編は連載開始の翌年に発行されたものだ。
「No1. ルパン三世颯爽登場」から始まる14編を半世紀ぶりに再読した。この14編では五エ衛門はまだ登場しない。第1話では老探偵・明智小五郎が登場する。作品のテイストは後年のアニメとはかなり異なる。コメディタッチのエロティック・バイオレンスで、過激に尖っている。荒々しくてダイナミックなタッチの絵がカッコイイ。
この「青年コミック」が半世紀後に国民的アニメ作品に変貌するとは、当時の読者には想像もできなかったと思う。
そんな記事を読んでいて、大昔に買った原作漫画がまだあるのではと思いあたり、本棚の奥を探索すると、1968年発行の『漫画アクション・コミックス』が出てきた。『漫画アクション』連載の『ルパン三世』のNo1からNo14までを収録した総集編である。
調べてみると『ルパン三世』は『漫画アクション』の創刊号(1967年8月10日号)から連載が始まっている。私の持っている総集編は連載開始の翌年に発行されたものだ。
「No1. ルパン三世颯爽登場」から始まる14編を半世紀ぶりに再読した。この14編では五エ衛門はまだ登場しない。第1話では老探偵・明智小五郎が登場する。作品のテイストは後年のアニメとはかなり異なる。コメディタッチのエロティック・バイオレンスで、過激に尖っている。荒々しくてダイナミックなタッチの絵がカッコイイ。
この「青年コミック」が半世紀後に国民的アニメ作品に変貌するとは、当時の読者には想像もできなかったと思う。
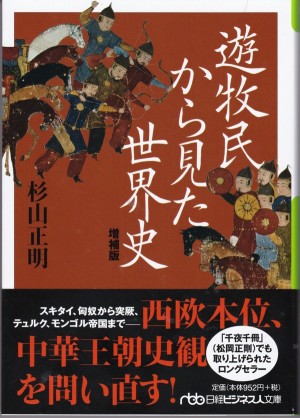




最近のコメント