ヨーロッパ中世の概説書で『大聖堂』の世界を検証 ― 2016年04月03日
◎ヨーロッパ中世の概説書を読む
書架に並べてある世界史シリーズ本の中からヨーロッパ中世を扱った次の2冊を引っ張り出して読んだ。
『中世の光と影(大世界史 7)』(堀米庸三/文藝春秋/1966.12)
『西ヨーロッパ世界の形成(世界の歴史 10)』(佐藤彰一、池上俊一/中央公論社/1997.5)
前者は約50年前、後者は約20年前の本だ。元来、私はヨーロッパ中世には無知で、さほど関心もなかった。なのに上記の本を読んだのは、ケン・フォレットのエンタメ大長編『大聖堂』『大聖堂 ― 果てしなき世界』(以下『大聖堂・続編』)を読んで、この小説の舞台になった時代の概要を知りたいと思ったからだ。
『大聖堂』の舞台は12世紀イギリスの架空の町、『大聖堂・続編』は同じ町の14世紀の物語だ。職人、商人、修道士、騎士などが活躍する壮大なフィクションだが、歴史上の人物も多少は登場する。前者ではイングランド王のヘンリー1世、スティーブン1世、ヘンリー2世、カンタベリー大司教のトマス・ベケットなど、後者ではエドワード3世、プリンス・オブ・ウェールズなどだ。いずれも高校の世界史には出てこない人々だ。高校世界史よりは多少詳しい概説書を読んで史実を把握しておこうと思った。
◎ヨーロッパ中世千年史に既視感
『中世の光と影』『西ヨーロッパ世界の形成』のいずれにも巻末に年表があり、そこには4世紀から15世紀までの約千年の出来事が記載されている。ヨーロッパの中世は千年も続いたのかと、あらためてその長さに驚いた。
『中世の光と影』を読み進めていて、かすかな既視感がわいた。ヨーロッパ中世史の本など読んだことがないはずだがと思いつつ記憶を探り、約1年前に読了したギボンの『ローマ帝国衰亡史』と重なっていることに気づいた。あの長大な史書の後半5巻は西ローマ帝国滅亡の5世紀からコンスタンティノポリス陥落の1453年までの約千年を扱っていた。考えてみれば『ローマ帝国衰亡史』は古代史+中世史の本だった。
にもかかわらず、私は『大聖堂』『大聖堂・続編』を読みながらギボンを想起することはなく、自分にとってヨーロッパ中世史は暗闇のようなものだと感じていた。要は読書しても何も残っていないということで、悲しいことではある。とは言え、18世紀英国の啓蒙家ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において自分の国イギリスの中世にはあまり言及していない。かつてのローマ帝国の中心だった地中海世界から見ればイギリスは辺境だったからだろうか。いずれにしても、私はギボンの世界に重なりあいを感じることなく『大聖堂』『大聖堂・続編』を読んだのだ。
◎教科書的な概説書ではなかった
では、『中世の光と影』『西ヨーロッパ世界の形成』を読んで、『大聖堂』『大聖堂・続編』の世界をより深く知ることができたか。答えはノーでもありイエスでもある。
『中世の光と影』も『西ヨーロッパ世界の形成』も歴史年表を詳述するような教科書的な概説書ではなかった。史実の羅列ではなく著者が中世史をどのように捉えているかを述べた本で、『大聖堂』『大聖堂・続編』に登場する実在の国王などに関する記述はほとんどなかった。
『大聖堂』は12世紀半ばの約50年、『大聖堂・続編』は14世紀半ばの約30年の物語で、千年の中世史の中のわずかな時間に過ぎない。また、小説の舞台イギリスはヨーロッパ中世史の中心地域からはやや外れている。1冊で千年を語る概説書の記述から漏れ落ちるのは仕方ない。小説に登場する実在の人物に関する史実を確認したいという目的は果たされなかった。
ただし、トマス・ベケット大司教の暗殺は『中世の光と影』で言及されていた。フィクションの主要人物を暗殺者に仕立て、小説に史実を巧みに組み込んでいることがわかり、拾いものだった。
『中世の光と影』は、紀行文を随所に挿入した歴史エッセイ風の本で、法王と皇帝とのせめぎあいでヨーロッパが作られていくさまが描かれていて、中世という時代の様子が俯瞰できた。また、教会建築がロマネスク様式からゴシック様式に転換していく様子はかなり詳しく書かれている。尖頭アーチ、肋骨式横断アーチ、交叉穹窿などの建築技術が図解入りで解説されているので、『大聖堂』の世界の追体験になった。
◎やはり史実を確認できた
『西ヨーロッパ世界の形成』は予想外の概説書だった。教科書的な史実の解説などほとんどない。読者が基本的な史実を把握していることを前提にした本のようだ。
社会史あるいは民衆史とも言える内容で、少々まごついたが、意外にこれが面白い。都市、農村、森、修道院などについてかなり細かく書かれている。付録の月報は著者二人と日本中世史の大家・網野善彦氏との座談会で、網野氏は「新しい中世史像を知ることができて大きな収穫がありました」と持ち上げている。
『大聖堂』『大聖堂・続編』には実在した国王や大司教も登場するが、主な登場人物は石工、羊毛商人、大工、機織り屋、農民、修道士、修道院長、托鉢修道士、司教、騎士、領主など多様は人々だ。また、主な舞台は修道院、その周辺の町、定期的に開催される市、森、農村などである。『西ヨーロッパ世界の形成』は、このような多様な人々や場所についてかなり詳しく記述している。
私は「縮絨(しゅくじゅう)」という言葉を『大聖堂』で初めて知った。毛織物を仕上げる工程の一つで、かなりの重労働だそうだ。小説では、主人公が縮絨を容易にするため水車を使う方法を「発明」するシーンがある。『西ヨーロッパ世界の形成』で、12世紀頃には水車が縮絨に使われるようになったとの記述に接し、虚実の遭遇に軽い感動を覚えた。また、『大聖堂・続編』では染色に工夫する印象的なシーンがあり、『西ヨーロッパ世界の形成』には、当時の染色職人や染色技術に関する興味深い記述がある。小説との暗合を感じた。
数えあげればきりがないが、『西ヨーロッパ世界の形成』には『大聖堂』『大聖堂・続編』の世界のディティールに関連した記述が多い。歴史上の人物などとは別次元で、小説世界に展開されたあれこれに史実の裏付けがあることを『西ヨーロッパ世界の形成』で確認できたのは想定外の収穫だった。つまりは、ケン・フォレットが最新(執筆当時)の歴史学や考古学の成果をふまえて小説を書いたことが確認できたのである。
書架に並べてある世界史シリーズ本の中からヨーロッパ中世を扱った次の2冊を引っ張り出して読んだ。
『中世の光と影(大世界史 7)』(堀米庸三/文藝春秋/1966.12)
『西ヨーロッパ世界の形成(世界の歴史 10)』(佐藤彰一、池上俊一/中央公論社/1997.5)
前者は約50年前、後者は約20年前の本だ。元来、私はヨーロッパ中世には無知で、さほど関心もなかった。なのに上記の本を読んだのは、ケン・フォレットのエンタメ大長編『大聖堂』『大聖堂 ― 果てしなき世界』(以下『大聖堂・続編』)を読んで、この小説の舞台になった時代の概要を知りたいと思ったからだ。
『大聖堂』の舞台は12世紀イギリスの架空の町、『大聖堂・続編』は同じ町の14世紀の物語だ。職人、商人、修道士、騎士などが活躍する壮大なフィクションだが、歴史上の人物も多少は登場する。前者ではイングランド王のヘンリー1世、スティーブン1世、ヘンリー2世、カンタベリー大司教のトマス・ベケットなど、後者ではエドワード3世、プリンス・オブ・ウェールズなどだ。いずれも高校の世界史には出てこない人々だ。高校世界史よりは多少詳しい概説書を読んで史実を把握しておこうと思った。
◎ヨーロッパ中世千年史に既視感
『中世の光と影』『西ヨーロッパ世界の形成』のいずれにも巻末に年表があり、そこには4世紀から15世紀までの約千年の出来事が記載されている。ヨーロッパの中世は千年も続いたのかと、あらためてその長さに驚いた。
『中世の光と影』を読み進めていて、かすかな既視感がわいた。ヨーロッパ中世史の本など読んだことがないはずだがと思いつつ記憶を探り、約1年前に読了したギボンの『ローマ帝国衰亡史』と重なっていることに気づいた。あの長大な史書の後半5巻は西ローマ帝国滅亡の5世紀からコンスタンティノポリス陥落の1453年までの約千年を扱っていた。考えてみれば『ローマ帝国衰亡史』は古代史+中世史の本だった。
にもかかわらず、私は『大聖堂』『大聖堂・続編』を読みながらギボンを想起することはなく、自分にとってヨーロッパ中世史は暗闇のようなものだと感じていた。要は読書しても何も残っていないということで、悲しいことではある。とは言え、18世紀英国の啓蒙家ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において自分の国イギリスの中世にはあまり言及していない。かつてのローマ帝国の中心だった地中海世界から見ればイギリスは辺境だったからだろうか。いずれにしても、私はギボンの世界に重なりあいを感じることなく『大聖堂』『大聖堂・続編』を読んだのだ。
◎教科書的な概説書ではなかった
では、『中世の光と影』『西ヨーロッパ世界の形成』を読んで、『大聖堂』『大聖堂・続編』の世界をより深く知ることができたか。答えはノーでもありイエスでもある。
『中世の光と影』も『西ヨーロッパ世界の形成』も歴史年表を詳述するような教科書的な概説書ではなかった。史実の羅列ではなく著者が中世史をどのように捉えているかを述べた本で、『大聖堂』『大聖堂・続編』に登場する実在の国王などに関する記述はほとんどなかった。
『大聖堂』は12世紀半ばの約50年、『大聖堂・続編』は14世紀半ばの約30年の物語で、千年の中世史の中のわずかな時間に過ぎない。また、小説の舞台イギリスはヨーロッパ中世史の中心地域からはやや外れている。1冊で千年を語る概説書の記述から漏れ落ちるのは仕方ない。小説に登場する実在の人物に関する史実を確認したいという目的は果たされなかった。
ただし、トマス・ベケット大司教の暗殺は『中世の光と影』で言及されていた。フィクションの主要人物を暗殺者に仕立て、小説に史実を巧みに組み込んでいることがわかり、拾いものだった。
『中世の光と影』は、紀行文を随所に挿入した歴史エッセイ風の本で、法王と皇帝とのせめぎあいでヨーロッパが作られていくさまが描かれていて、中世という時代の様子が俯瞰できた。また、教会建築がロマネスク様式からゴシック様式に転換していく様子はかなり詳しく書かれている。尖頭アーチ、肋骨式横断アーチ、交叉穹窿などの建築技術が図解入りで解説されているので、『大聖堂』の世界の追体験になった。
◎やはり史実を確認できた
『西ヨーロッパ世界の形成』は予想外の概説書だった。教科書的な史実の解説などほとんどない。読者が基本的な史実を把握していることを前提にした本のようだ。
社会史あるいは民衆史とも言える内容で、少々まごついたが、意外にこれが面白い。都市、農村、森、修道院などについてかなり細かく書かれている。付録の月報は著者二人と日本中世史の大家・網野善彦氏との座談会で、網野氏は「新しい中世史像を知ることができて大きな収穫がありました」と持ち上げている。
『大聖堂』『大聖堂・続編』には実在した国王や大司教も登場するが、主な登場人物は石工、羊毛商人、大工、機織り屋、農民、修道士、修道院長、托鉢修道士、司教、騎士、領主など多様は人々だ。また、主な舞台は修道院、その周辺の町、定期的に開催される市、森、農村などである。『西ヨーロッパ世界の形成』は、このような多様な人々や場所についてかなり詳しく記述している。
私は「縮絨(しゅくじゅう)」という言葉を『大聖堂』で初めて知った。毛織物を仕上げる工程の一つで、かなりの重労働だそうだ。小説では、主人公が縮絨を容易にするため水車を使う方法を「発明」するシーンがある。『西ヨーロッパ世界の形成』で、12世紀頃には水車が縮絨に使われるようになったとの記述に接し、虚実の遭遇に軽い感動を覚えた。また、『大聖堂・続編』では染色に工夫する印象的なシーンがあり、『西ヨーロッパ世界の形成』には、当時の染色職人や染色技術に関する興味深い記述がある。小説との暗合を感じた。
数えあげればきりがないが、『西ヨーロッパ世界の形成』には『大聖堂』『大聖堂・続編』の世界のディティールに関連した記述が多い。歴史上の人物などとは別次元で、小説世界に展開されたあれこれに史実の裏付けがあることを『西ヨーロッパ世界の形成』で確認できたのは想定外の収穫だった。つまりは、ケン・フォレットが最新(執筆当時)の歴史学や考古学の成果をふまえて小説を書いたことが確認できたのである。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2016/04/03/8064719/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
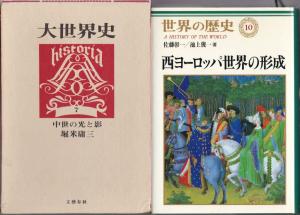
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。