理念なき過激派が歴史を動かした---薩長への怒りの書 ― 2011年06月23日
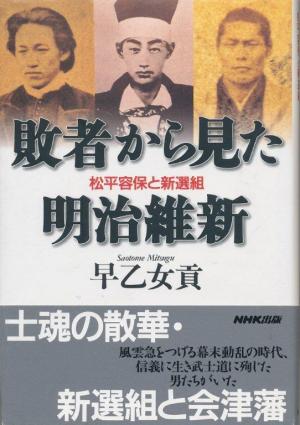
NHKの大河ドラマはほとんど観ていないが、数年前の「新選組」は観た。そのとき、新選組にハマって読んだ本の一つが『敗者から見た明治維新:松平容保と新撰組』(早乙女貢/NHK出版)だった。このたび、幕末史を振り返ってみようと思い、再読した。
会津藩士の末裔である早乙女貢氏の薩長への怒りが伝わってくる本だ。早乙女氏は、明治維新の真実は薩長の強権によって抹殺されたと主張する。薩長の立場で語られる幕末維新の様相をほぼ全否定し、会津藩から見た歴史こそが実相であるとした本書は、ある意味ではわかりやすい本である。
著者が評価するのは京都守護職だった会津藩主・松平容保であり、新選組である。最大の悪者は長州、次いで薩摩だ。徳川慶喜も非難の対象になっている。
私は本書を読んで、さほど極端な見解だとは思わなかった。会津藩からは、歴史がこのように見えるのは当然だと思う。共感できる部分も多い。
松平容保こそが純粋な勤皇で、薩長は天皇を利用しただけだという主張も間違っていない。
孝明天皇は松平容保を心の友と見ていたそうだが、その容保は薩長によって逆賊にされてしまう。蛤御門の変で天皇に大砲をぶっぱなした長州が勤皇で、鳥羽伏見の戦いで錦旗を見て刃を納めた会津や新選組が逆賊というのは、やはり、おかしな話だ。
会津藩は明治になってからも新政府から苛酷な仕打ちを受ける。これは、不条理な受難史ロマンのようでもある。
早乙女氏は明治の元勲たちを「元テロリスト」と指弾する。間違いではない。ただし、元テロリストが政治の中枢を掌握するのは珍しいことではない。それが「革命」の姿のひとつだろう。やはり、幕末は革命だったのだ。
早乙女氏は薩長だけでなく、徳川慶喜にも手厳しい。松平容保を裏切った小心で短慮で無責任な卑怯者としている。この評価は一方的で、徳川慶喜にはちょっと気の毒だと思う。本人は、そんなことを気にしないタイプの人だったかもしれないが。
本書では「勤皇攘夷」の欺瞞性も論じている。早乙女氏は、攘夷は一部の若者たちに蔓延した熱狂だとし、「人生を知らぬ若者には遠望が利かない。目前の事象だけで行動に走りたがるのだ」と、短慮な若者たちを批判している。
また、「勤皇攘夷」はお調子もののモダンボーイたちが振りまわす観念で、京都で「勤皇攘夷」を叫んでいれば、飯が食えて、酒や女にありつけたと述べている。「勤皇攘夷」を標榜して総会屋のような強請をする者もいたという。
もちろん、真面目に「勤皇攘夷」を追究している者もいただろうが、付和雷同するお調子ものが少なくなかっただろうことは、わが人生経験からも容易に想像できる。若者とは、そういう存在でもあるのだ。
また、早乙女氏は「薩長土肥勢力による徳川幕府の打倒には統一された理念はなく、場当たり的な行動の結果だった」としている。半藤一利氏と似た見解だ。
倒幕の理念はなかったとしても、ある種の恨み(復讐心)はあったかもしれない。早乙女氏が薩長を恨むのと同じように、幕末の長州は幕府に対して安政の大獄(彼らの師・吉田松陰が殺された)や長州征伐への恨みを抱いていたかもしれない。また、会津や新選組に対しては蛤御門の変や池田屋事件への仕返し気分があったかもしれない。
単に恨みや逆恨みを積み重ねても「理念」は出てこない。そんな要素を洗い流したあとに残る倒幕の必然性があれば、それが歴史を動かす理念だろうか。
早乙女氏は、薩長の「理念なき革命」が現代の諸悪の元凶だ、とまで主張している。次のような調子だ。
「長州人の野望が、近世日本の精神と文化を破壊し、人間性を堕し、救い難いほどの今日の退廃した社会の源流をなしたことは、政界の腐敗ぶり、社会不安を醸成する日々の残虐な少年犯罪などに歴然たるものがある。」
「この流血の明治維新が、どれだけ日本の美しい精神を打ち砕き、人間性を堕落せしめたか。会津藩に見る日新館教育の持つ道徳性、家族愛、武士道の純粋さとは、あまりに違いすぎた。」
坊主憎けりゃ…という気もするのだが。
いずれにしても、著者の思惑とは異なり、本書が図らずも明らかにしているのは、理念なき過激派でも(だからこそ)もつことができた「歴史を動かす力」の大きさである。
会津藩士の末裔である早乙女貢氏の薩長への怒りが伝わってくる本だ。早乙女氏は、明治維新の真実は薩長の強権によって抹殺されたと主張する。薩長の立場で語られる幕末維新の様相をほぼ全否定し、会津藩から見た歴史こそが実相であるとした本書は、ある意味ではわかりやすい本である。
著者が評価するのは京都守護職だった会津藩主・松平容保であり、新選組である。最大の悪者は長州、次いで薩摩だ。徳川慶喜も非難の対象になっている。
私は本書を読んで、さほど極端な見解だとは思わなかった。会津藩からは、歴史がこのように見えるのは当然だと思う。共感できる部分も多い。
松平容保こそが純粋な勤皇で、薩長は天皇を利用しただけだという主張も間違っていない。
孝明天皇は松平容保を心の友と見ていたそうだが、その容保は薩長によって逆賊にされてしまう。蛤御門の変で天皇に大砲をぶっぱなした長州が勤皇で、鳥羽伏見の戦いで錦旗を見て刃を納めた会津や新選組が逆賊というのは、やはり、おかしな話だ。
会津藩は明治になってからも新政府から苛酷な仕打ちを受ける。これは、不条理な受難史ロマンのようでもある。
早乙女氏は明治の元勲たちを「元テロリスト」と指弾する。間違いではない。ただし、元テロリストが政治の中枢を掌握するのは珍しいことではない。それが「革命」の姿のひとつだろう。やはり、幕末は革命だったのだ。
早乙女氏は薩長だけでなく、徳川慶喜にも手厳しい。松平容保を裏切った小心で短慮で無責任な卑怯者としている。この評価は一方的で、徳川慶喜にはちょっと気の毒だと思う。本人は、そんなことを気にしないタイプの人だったかもしれないが。
本書では「勤皇攘夷」の欺瞞性も論じている。早乙女氏は、攘夷は一部の若者たちに蔓延した熱狂だとし、「人生を知らぬ若者には遠望が利かない。目前の事象だけで行動に走りたがるのだ」と、短慮な若者たちを批判している。
また、「勤皇攘夷」はお調子もののモダンボーイたちが振りまわす観念で、京都で「勤皇攘夷」を叫んでいれば、飯が食えて、酒や女にありつけたと述べている。「勤皇攘夷」を標榜して総会屋のような強請をする者もいたという。
もちろん、真面目に「勤皇攘夷」を追究している者もいただろうが、付和雷同するお調子ものが少なくなかっただろうことは、わが人生経験からも容易に想像できる。若者とは、そういう存在でもあるのだ。
また、早乙女氏は「薩長土肥勢力による徳川幕府の打倒には統一された理念はなく、場当たり的な行動の結果だった」としている。半藤一利氏と似た見解だ。
倒幕の理念はなかったとしても、ある種の恨み(復讐心)はあったかもしれない。早乙女氏が薩長を恨むのと同じように、幕末の長州は幕府に対して安政の大獄(彼らの師・吉田松陰が殺された)や長州征伐への恨みを抱いていたかもしれない。また、会津や新選組に対しては蛤御門の変や池田屋事件への仕返し気分があったかもしれない。
単に恨みや逆恨みを積み重ねても「理念」は出てこない。そんな要素を洗い流したあとに残る倒幕の必然性があれば、それが歴史を動かす理念だろうか。
早乙女氏は、薩長の「理念なき革命」が現代の諸悪の元凶だ、とまで主張している。次のような調子だ。
「長州人の野望が、近世日本の精神と文化を破壊し、人間性を堕し、救い難いほどの今日の退廃した社会の源流をなしたことは、政界の腐敗ぶり、社会不安を醸成する日々の残虐な少年犯罪などに歴然たるものがある。」
「この流血の明治維新が、どれだけ日本の美しい精神を打ち砕き、人間性を堕落せしめたか。会津藩に見る日新館教育の持つ道徳性、家族愛、武士道の純粋さとは、あまりに違いすぎた。」
坊主憎けりゃ…という気もするのだが。
いずれにしても、著者の思惑とは異なり、本書が図らずも明らかにしているのは、理念なき過激派でも(だからこそ)もつことができた「歴史を動かす力」の大きさである。
最近のコメント