那覇で風速55メートルを体験した ― 2011年06月03日
先週末から沖縄旅行をした。那覇市内に滞在しただけだったが、タイミングが悪かったのか良かったのか台風2号に遭遇した。
那覇市に台風が襲来したのは5月28日の夜だった。前日から台風に備えた準備行動が始まっていた。マンションのアルミサッシの溝に新聞紙を詰める作業なども目撃した。そこまでやる必要があるのかと、台風襲来への準備作業の大袈裟さにちょっと違和感をおぼえた。
しかし、28日夜の強風を体験して、一連の準備作業が納得できた。あの夜、那覇市では最大瞬間風速55メートル以上を記録した。風速25メートル以上は暴風雨圏だから、風速55メートルは尋常ではない。私にとっては60数年の人生での初体験だったと思う。
台風一過の朝、町を歩くと根こそぎ倒れている樹木をいくつも目撃した。写真は那覇市旭町で撮影した一例だ。かなり大きな樹木が無惨な姿になっている。
数か月前、私は八ヶ岳の山荘(山小屋?)の敷地を「開墾」するために小さな立木を伐採して根を掘り起こしたことがある。軽い気持ちで根っ子の掘り出しにかっかたのだが、これが意外に手強かった。一時はあきらめようとも思った。1日で何とかなると思って手掛けた作業に数日を要し、やっとのことで小さな樹木の根っ子を取り除いた。
そんな体験があって、樹木の根っ子のしぶとさを体験したばかりだったので、風であっけなく根こそぎにになった樹木の姿に、台風の威力を再認識した。
ありきたりの感想だが、天然自然の力の大きさと人間の力の微力を思い知った。もちろん、東日本大震災を経験したこととの連想もある。
科学技術の発展と産業革命によって人類が自然環境を変貌させる大きな力を持ってきたのは確かだ。しかし、その力はまだまだ微力であり、今も昔もわれわれは天然自然を畏怖する存在にすぎないのだと思う。
那覇市に台風が襲来したのは5月28日の夜だった。前日から台風に備えた準備行動が始まっていた。マンションのアルミサッシの溝に新聞紙を詰める作業なども目撃した。そこまでやる必要があるのかと、台風襲来への準備作業の大袈裟さにちょっと違和感をおぼえた。
しかし、28日夜の強風を体験して、一連の準備作業が納得できた。あの夜、那覇市では最大瞬間風速55メートル以上を記録した。風速25メートル以上は暴風雨圏だから、風速55メートルは尋常ではない。私にとっては60数年の人生での初体験だったと思う。
台風一過の朝、町を歩くと根こそぎ倒れている樹木をいくつも目撃した。写真は那覇市旭町で撮影した一例だ。かなり大きな樹木が無惨な姿になっている。
数か月前、私は八ヶ岳の山荘(山小屋?)の敷地を「開墾」するために小さな立木を伐採して根を掘り起こしたことがある。軽い気持ちで根っ子の掘り出しにかっかたのだが、これが意外に手強かった。一時はあきらめようとも思った。1日で何とかなると思って手掛けた作業に数日を要し、やっとのことで小さな樹木の根っ子を取り除いた。
そんな体験があって、樹木の根っ子のしぶとさを体験したばかりだったので、風であっけなく根こそぎにになった樹木の姿に、台風の威力を再認識した。
ありきたりの感想だが、天然自然の力の大きさと人間の力の微力を思い知った。もちろん、東日本大震災を経験したこととの連想もある。
科学技術の発展と産業革命によって人類が自然環境を変貌させる大きな力を持ってきたのは確かだ。しかし、その力はまだまだ微力であり、今も昔もわれわれは天然自然を畏怖する存在にすぎないのだと思う。
新聞週間の標語『新聞は世界平和の原子力』の記事かと思った ― 2011年06月09日
本日(2011年6月9日)の朝日新聞夕刊に「原発標語24年後の悔い」という見出しの記事が載っていた。
見出しを見た瞬間、新聞週間の標語の反省記事かと思った。しかし、そんな記事ではなかった。
24年前、福島県双葉町の標語コンクールで入選した『原子力明るい未来のエネルギー』という標語の作者に関する記事だった。当時、小学校6年生だった作者は現在35歳になり、避難生活を送っているそうだ。標語は、現在も双葉町の商店街に掲げられていて、作者は双葉町民に「うしろめたい気持ち」も感じる、と記事にある。
それほど面白い記事ではない。小学生時代に作った標語で「うしろめたい気持ち」になる必要はないし、もっと「うしろめたい」人はいくらでもいる筈だ。そういう人をドンドン取り上げるべきなのだ。そんな人はなかなか取材には口を開かないだろうが。
こんな標語を記事にするなら、1955年の新聞週間の標語『新聞は世界平和の原子力』を取り上げる方がよほど意義がある。
『新聞は世界平和の原子力』は新聞業界が選んだ標語だ。当時、原子力の平和利用=原子力発電を推進する旗振り役が新聞をはじめとするマスメディアだったのは間違いない。
私は、この標語を『科学記者』(柴田鉄治/岩波新書)という本で知ったが、最近、テレビの報道番組でも取り上げられたらしい。「鉄腕アトム」だって原子力の平和利用だし、私も子供の頃は原子力の平和利用に夢を感じていた。そのような風潮には何らかの根拠があった筈だ。うしろめたい気持で振り返る必要はないが、原発推進の歴史の淵源と展開を、より深く検討する必要はある。
現在、原子力発電の検証がメディアの大きな役割であることは間違いない。検証にあたっては、メディア(広告業界も含む)の果たしてきた役割もきちんと検証しなければならない。はたして、どこまでできるだろうか。
見出しを見た瞬間、新聞週間の標語の反省記事かと思った。しかし、そんな記事ではなかった。
24年前、福島県双葉町の標語コンクールで入選した『原子力明るい未来のエネルギー』という標語の作者に関する記事だった。当時、小学校6年生だった作者は現在35歳になり、避難生活を送っているそうだ。標語は、現在も双葉町の商店街に掲げられていて、作者は双葉町民に「うしろめたい気持ち」も感じる、と記事にある。
それほど面白い記事ではない。小学生時代に作った標語で「うしろめたい気持ち」になる必要はないし、もっと「うしろめたい」人はいくらでもいる筈だ。そういう人をドンドン取り上げるべきなのだ。そんな人はなかなか取材には口を開かないだろうが。
こんな標語を記事にするなら、1955年の新聞週間の標語『新聞は世界平和の原子力』を取り上げる方がよほど意義がある。
『新聞は世界平和の原子力』は新聞業界が選んだ標語だ。当時、原子力の平和利用=原子力発電を推進する旗振り役が新聞をはじめとするマスメディアだったのは間違いない。
私は、この標語を『科学記者』(柴田鉄治/岩波新書)という本で知ったが、最近、テレビの報道番組でも取り上げられたらしい。「鉄腕アトム」だって原子力の平和利用だし、私も子供の頃は原子力の平和利用に夢を感じていた。そのような風潮には何らかの根拠があった筈だ。うしろめたい気持で振り返る必要はないが、原発推進の歴史の淵源と展開を、より深く検討する必要はある。
現在、原子力発電の検証がメディアの大きな役割であることは間違いない。検証にあたっては、メディア(広告業界も含む)の果たしてきた役割もきちんと検証しなければならない。はたして、どこまでできるだろうか。
幕末維新に歴史変動の予兆を読み解くヒントを求める ― 2011年06月16日
これからしばらく(数カ月程度か?)、幕末史をプチテーマとして、少し勉強してみようと思う。きっかけは東日本大震災とその後の政治状況の混迷だ。
自然変動と歴史変動は連動していると指摘した『安政江戸地震:災害と政治権力』(野口武彦/ちくま学芸文庫)を読んだ影響もあり、歴史変動の始まりに直面しているような気分になったからだ。
歴史変動とは時代が大きく変わることだが、私自身は歴史変動を体験したことがあるだろうか。私が生きてきた六十数年の間に世の中は随分変わった。予想もしなかった変わり方をしたと言える。しかし、歴史変動と呼べるほどの激動を体験したとは言えない。
20世紀末から21世紀にかけて、ロシア、東欧、中国などでは歴史変動があった。同時代人として私はそれらを目撃はしたが、体験したわけではない。
仮に歴史変動を体験したとしても、歴史が大きく動くさまを同時代の人間がリアルタイムで把握するのは難しそうだ。
歴史が動くとはどういうことなのか、その実相をマクロやミクロの多様な視点から知るには、やはり、歴史から学ぶのが近道だと思う。
わが国が体験した最近の歴史変動は、1945年の敗戦と幕末維新である。1945年の敗戦は、そこに至るいろいろな経緯はあるにせよ、かなりわかりやすい歴史変動だった。それに比べて、幕末維新にはわかりにくい点が多い。大きな歴史の転換があったのは確かだが、その実態は複雑だ。
歴史変動の予感のなかで、われわれが直面している現代の動きを読み解くヒントを得るには、比較的単純な歴史変動だった敗戦よりは、群像が蠢いて歴史が動いた幕末維新を勉強する方か適切だと思う。
勉強と言っても、史料を渉猟して史学に踏み込もうなどという殊勝な向学心はない。自分なりに、歴史変動の実相を把握したいだけだ。情況の変化によって時代が動くさまをある程度追体験でき、世の中の劇的変化とはこういうことなのかと、それなりに納得できればと思う。
そして、大震災と原発事故の後にやってくるかもしれない時代の変わり目を、自分の目でつかみ取ることができれば面白いだろう。
そう簡単なことではなさそうだが。
手始めに『幕末気分』(野口武彦/講談社)と『幕末史』(半藤一利/新潮社)を読み、ついでに、以前読んだ『敗者から見た明治維新』(早乙女 貢/NHK出版)を再読した。
『幕末気分』を読んだのは、同じ著者の『安政江戸地震:災害と政治権力』の流れを汲む本だからだ。歴史変動に直面した幕末を「気分」という言葉でとらえている所に、時代を越えて私たちの同時代に通底するものを感じた。
半藤氏の『幕末史』は、幕末の通史のおさらいのつもりで読んだ。反骨の著者の語り下ろしは予想通りの面白さだった。
半藤氏は明治維新を「ヴィジョンなき革命」だったと見ている。この視点は、会津藩士の末裔でガチガチのアンチ薩長・早乙女氏に通じているように思い、『敗者から見た明治維新』を再読した。
この3冊で、気分を幕末維新へとシフトさせた。
自然変動と歴史変動は連動していると指摘した『安政江戸地震:災害と政治権力』(野口武彦/ちくま学芸文庫)を読んだ影響もあり、歴史変動の始まりに直面しているような気分になったからだ。
歴史変動とは時代が大きく変わることだが、私自身は歴史変動を体験したことがあるだろうか。私が生きてきた六十数年の間に世の中は随分変わった。予想もしなかった変わり方をしたと言える。しかし、歴史変動と呼べるほどの激動を体験したとは言えない。
20世紀末から21世紀にかけて、ロシア、東欧、中国などでは歴史変動があった。同時代人として私はそれらを目撃はしたが、体験したわけではない。
仮に歴史変動を体験したとしても、歴史が大きく動くさまを同時代の人間がリアルタイムで把握するのは難しそうだ。
歴史が動くとはどういうことなのか、その実相をマクロやミクロの多様な視点から知るには、やはり、歴史から学ぶのが近道だと思う。
わが国が体験した最近の歴史変動は、1945年の敗戦と幕末維新である。1945年の敗戦は、そこに至るいろいろな経緯はあるにせよ、かなりわかりやすい歴史変動だった。それに比べて、幕末維新にはわかりにくい点が多い。大きな歴史の転換があったのは確かだが、その実態は複雑だ。
歴史変動の予感のなかで、われわれが直面している現代の動きを読み解くヒントを得るには、比較的単純な歴史変動だった敗戦よりは、群像が蠢いて歴史が動いた幕末維新を勉強する方か適切だと思う。
勉強と言っても、史料を渉猟して史学に踏み込もうなどという殊勝な向学心はない。自分なりに、歴史変動の実相を把握したいだけだ。情況の変化によって時代が動くさまをある程度追体験でき、世の中の劇的変化とはこういうことなのかと、それなりに納得できればと思う。
そして、大震災と原発事故の後にやってくるかもしれない時代の変わり目を、自分の目でつかみ取ることができれば面白いだろう。
そう簡単なことではなさそうだが。
手始めに『幕末気分』(野口武彦/講談社)と『幕末史』(半藤一利/新潮社)を読み、ついでに、以前読んだ『敗者から見た明治維新』(早乙女 貢/NHK出版)を再読した。
『幕末気分』を読んだのは、同じ著者の『安政江戸地震:災害と政治権力』の流れを汲む本だからだ。歴史変動に直面した幕末を「気分」という言葉でとらえている所に、時代を越えて私たちの同時代に通底するものを感じた。
半藤氏の『幕末史』は、幕末の通史のおさらいのつもりで読んだ。反骨の著者の語り下ろしは予想通りの面白さだった。
半藤氏は明治維新を「ヴィジョンなき革命」だったと見ている。この視点は、会津藩士の末裔でガチガチのアンチ薩長・早乙女氏に通じているように思い、『敗者から見た明治維新』を再読した。
この3冊で、気分を幕末維新へとシフトさせた。
幕末気分とはソワソワ、ワクワクする「軽さ」か ― 2011年06月19日
阪神大震災を体験した野口武彦氏は「歴史の変わり目には、自然災害と政治危機とは一つながりだという独特の現場感覚が日常的になる」という認識を得て、『安政江戸地震』を著わした。
それに続いて上梓したのが『幕末気分』(講談社/2002.2)である。帯には「大混乱時代に人はこう動く」とある。
『幕末気分』はタイトルが秀逸だ。「はしがき」で著者は次ような感慨を述べている。
「(阪神大震災後の漫画的な政局を見て)幕末政治家もこうだったのではないか。そう思ったらいっぺんに親近感が涌いた。先が見えず、まわりも見えず、一寸先の闇を手探る歴史の時間帯が再度到来しているのだ。心はすっかり幕末気分である。」
9年前に書かれた文章だが、東日本大震災とその後の政治の混迷を体験しつつある2011年の現在こそ、この幕末気分がぴったりくる。
『幕末気分』は、幕末のさまざまな情景を描いた7編で構成されている。それぞれのタイトルと論評対象は以下の通りだ。
・幕末の遊兵隊
→第2次長州征伐に参加した幕府軍の行状
・帰ってきた妖怪
→蛮社の獄で洋学者を弾圧した鳥居耀蔵が出獄したきた明治期の晩年
・地下で哭く骨
→井伊直弼の謀臣として名を残した長野主膳
・道頓堀の四谷怪談
→第2次長州征伐当時の大阪の芝居小屋での出来事など
・徳川慶喜のブリュメール十八日
→鳥羽伏見の戦いにおける慶喜の大阪脱出
・吉原歩兵騒乱記
→狼藉が原因で吉原で襲撃された歩兵の報復に吉原を攻撃した幕府歩兵隊
・上野モンマルトル1868
上野の山の彰義隊の戦い
それぞれにユニークな視点で語られていて興味深い。なかでも、「悲壮な将軍の下の遊惰な兵士たち」のびっくりするような実態を描いた「幕末の遊兵隊」が抜群に面白い。著者は幕府軍の兵士たちを次のように描いている。
「(幕府軍の兵士たちの)日々の無責任な軽佻浮薄は、いかなる情勢に対しても雑俳と駄洒落と茶番で対応することしか知らない江戸文明をたっぷり吸収している。年季が入っているのだ。深刻になると冗談で切り抜ける。必死になるなんてヤボな真似はしない。こうなると立派という他ないほど、江戸っ子の骨髄にしみこんで死んでも直らぬスタイルなのである。このノンシャランスと長州兵の一心不乱の間には大きなギャップがある。」
ここで描かれている幕末の「気分」は異常なほどに能天気な明るさである。
また、『道頓堀の四谷怪談』では、この時代を次のように表現している。
「人生が芝居のようだとはごくありふれた言い回しである。だが一時代の人間がみんな一斉にそう思い始めたとなると、もはや尋常ではない。実際その通りのことが起きていた時代が幕末だった。」
本書全体に流れるトーンは、幕末期の人々の能天気とパフォーマンス感覚であり、国家の大事を見ずに権力闘争や保身に明けくれる政治家たちの「小者」ぶりである。ある意味での「軽さ」とも言える。
私が子供の頃に接した幕末物のお話では、勤皇の志士(正義の味方である)が「日本の夜明けは近い」と見栄を切るのが定番だった。こんな科白によって「暗い封建時代が終わろうとしていて、明るい文明開化の時代が近づいている」という気分になったものだ。
しかし、幕末期を生きた人々で、その時代を「暗い」と感じていた人はあまりいなかったのではなかろうか。
尊王攘夷のテロが横行した数年などは、物情騒然とした非日常的時代だったと思うが、多くの人々はその時代を面白おかしく楽しんでいたのかもしれない。
「幕末気分」とは、世紀末気分や末世気分のような鬱陶しいものとは違うようだ。危機意識をはらんだ軽薄さのようなもので、ソワソワ・ウカウカするような気分だったように思える。
考えてみれば、幕末期に活躍した人々の多くは「軽快、軽薄、無節操、無責任」といった「軽さ」をもっていたように思える。「幕末気分」とは、そんな軽さを醸成する空気かもしれない。軽い時代が到来したからこそ、時代が動いてしまった、そのように思えてきた。
もちろん、現代も軽い時代だと思う。
それに続いて上梓したのが『幕末気分』(講談社/2002.2)である。帯には「大混乱時代に人はこう動く」とある。
『幕末気分』はタイトルが秀逸だ。「はしがき」で著者は次ような感慨を述べている。
「(阪神大震災後の漫画的な政局を見て)幕末政治家もこうだったのではないか。そう思ったらいっぺんに親近感が涌いた。先が見えず、まわりも見えず、一寸先の闇を手探る歴史の時間帯が再度到来しているのだ。心はすっかり幕末気分である。」
9年前に書かれた文章だが、東日本大震災とその後の政治の混迷を体験しつつある2011年の現在こそ、この幕末気分がぴったりくる。
『幕末気分』は、幕末のさまざまな情景を描いた7編で構成されている。それぞれのタイトルと論評対象は以下の通りだ。
・幕末の遊兵隊
→第2次長州征伐に参加した幕府軍の行状
・帰ってきた妖怪
→蛮社の獄で洋学者を弾圧した鳥居耀蔵が出獄したきた明治期の晩年
・地下で哭く骨
→井伊直弼の謀臣として名を残した長野主膳
・道頓堀の四谷怪談
→第2次長州征伐当時の大阪の芝居小屋での出来事など
・徳川慶喜のブリュメール十八日
→鳥羽伏見の戦いにおける慶喜の大阪脱出
・吉原歩兵騒乱記
→狼藉が原因で吉原で襲撃された歩兵の報復に吉原を攻撃した幕府歩兵隊
・上野モンマルトル1868
上野の山の彰義隊の戦い
それぞれにユニークな視点で語られていて興味深い。なかでも、「悲壮な将軍の下の遊惰な兵士たち」のびっくりするような実態を描いた「幕末の遊兵隊」が抜群に面白い。著者は幕府軍の兵士たちを次のように描いている。
「(幕府軍の兵士たちの)日々の無責任な軽佻浮薄は、いかなる情勢に対しても雑俳と駄洒落と茶番で対応することしか知らない江戸文明をたっぷり吸収している。年季が入っているのだ。深刻になると冗談で切り抜ける。必死になるなんてヤボな真似はしない。こうなると立派という他ないほど、江戸っ子の骨髄にしみこんで死んでも直らぬスタイルなのである。このノンシャランスと長州兵の一心不乱の間には大きなギャップがある。」
ここで描かれている幕末の「気分」は異常なほどに能天気な明るさである。
また、『道頓堀の四谷怪談』では、この時代を次のように表現している。
「人生が芝居のようだとはごくありふれた言い回しである。だが一時代の人間がみんな一斉にそう思い始めたとなると、もはや尋常ではない。実際その通りのことが起きていた時代が幕末だった。」
本書全体に流れるトーンは、幕末期の人々の能天気とパフォーマンス感覚であり、国家の大事を見ずに権力闘争や保身に明けくれる政治家たちの「小者」ぶりである。ある意味での「軽さ」とも言える。
私が子供の頃に接した幕末物のお話では、勤皇の志士(正義の味方である)が「日本の夜明けは近い」と見栄を切るのが定番だった。こんな科白によって「暗い封建時代が終わろうとしていて、明るい文明開化の時代が近づいている」という気分になったものだ。
しかし、幕末期を生きた人々で、その時代を「暗い」と感じていた人はあまりいなかったのではなかろうか。
尊王攘夷のテロが横行した数年などは、物情騒然とした非日常的時代だったと思うが、多くの人々はその時代を面白おかしく楽しんでいたのかもしれない。
「幕末気分」とは、世紀末気分や末世気分のような鬱陶しいものとは違うようだ。危機意識をはらんだ軽薄さのようなもので、ソワソワ・ウカウカするような気分だったように思える。
考えてみれば、幕末期に活躍した人々の多くは「軽快、軽薄、無節操、無責任」といった「軽さ」をもっていたように思える。「幕末気分」とは、そんな軽さを醸成する空気かもしれない。軽い時代が到来したからこそ、時代が動いてしまった、そのように思えてきた。
もちろん、現代も軽い時代だと思う。
戊辰戦争は無駄で阿呆な戦争だった ― 2011年06月21日
『幕末史』(新潮社)を語り下ろした半藤一利氏には江戸っ子のイメージがある。しかし、父の生家が長岡で、幼少の頃、祖母から「薩長なんて連中はそもそも泥棒だ」と繰り返し聞かされたそうだ。戊申戦争で逆賊にされてしまった長岡の血を引いているせいもあり、本書の「はじめの章」で著者は「『反薩長史観』となることは請合いであります」と宣言している。
本書で扱う時代はペリー来航の1853年から西南戦争の1877年までの24年間だ。西南戦争は明治10年なので、24年の内の10年は明治であり、この間の歴史を語るなら「幕末維新史」とする方が適切のように思える。
しかし、西南戦争までをあえて「幕末史」とした所に著者の史観がある。「維新」なんてフィクションだという見解である。
歴史は、それを語る人の立場によって様相が異なってくる。歴史上の人物の誰に肩入れして語るか、誰に共感しているかによって、歴史はいろいろな見え方をする。幕末期は主人公がはっきりしない群像の時代なので、共感する人物の違いによって情景が違って見える傾向が特に強いように思われる。
半藤氏がひいきにしているのは勝海舟である。明治32年まで生きた勝海舟は、多くの歴史座談を残している。晩年の勝海舟は、誰のことでもつい昨日会ったかのような調子で気さくに語ったそうだ。
幕末期に活躍した人物たちを、身近な知り合いとして生き生きと語る勝海舟のさまは、出版社の求めに応じて幕末史を歴史講談のように語る半藤氏に似ているところがある。
もちろん、著者は幕末を目撃しているわけではないが、二十数人の聴衆を前にした講義の縦横な語り口は魅力的である。話し言葉なので、登場人物も「阿部さん(阿部正弘)、堀田さん(堀田正睦)」、「わが愛する勝つぁん(勝海舟)」といった調子になる。あたかも目撃したかのような名調子になるのは、熟達の編集者の名人芸だ。
半藤氏が勝海舟を評価するのは、幕府や薩長という枠を超えた国のかたちが見えていた人物と見なしているからだ。半藤氏は次のように語っている。
「幕末にはずいぶんいろんな人が出てきますが、自分の藩がどうのといった意識や利害損得を超越して、日本国ということを大局的に見据えてきちんと事にあたったのは勝一人だったと私は思っています。」
西郷隆盛や坂本龍馬に新たな国家像を吹き込んだのは勝海舟であり、船中八策のオリジナルは勝海舟と大久保一翁にあると指摘している。
そんな勝海舟に共感する著者が語る幕末史のポイントは次の2点だ。
(1) 戊辰戦争は無駄で阿呆な戦争だった。薩長が天皇をうまく使って国家を乗っ取っただけの権力闘争・暴力革命だった。
(2) 戊辰戦争に勝利した薩長には、新たな国家の青写真も設計図もヴィジョンもなかった。
本書が西南戦争と大久保利通暗殺までを一区切りとしているのは、西南戦争のきっかけになった征韓論の論争を戊申戦争の権力闘争の継続だったと見なしているからだ。暴力革命の決着までを幕末史としているのだ。
戊申戦争を無駄で阿呆な戦争と見る視点は、その直前の大政奉還によって歴史はすでに大きく動いたと見なすことに通じる。
戊申戦争がなくても、この時期に日本は封建社会から近代社会へ転換したはずであり、その場合の新たな国家の姿は薩長が作った明治国家とは違った形になったに違いない……そんな思いが伝わってくる本である。
ヴィジョンなき薩長が作り上げたのは「維新」という言葉であり、皇国史観だった。戊申戦争がなければ、天皇制や天皇の位置づけも、その後の歴史とはかなり違った形になったはずだ。
戊辰戦争がなかったとすれば、徳川慶喜がその後の時代の主役を担った可能性が高いように思われるが、半藤氏は徳川慶喜にはあまり同情的ではない。それほど高く評価していないようだ。慶喜よりは家茂が好きだったと思われる勝海舟の目を通した評価なのかもしれない。
それはともかく、本書を読んであらためて感じたのは「理念やヴィジョンがなくても、ある種の熱気だけで世の中が大きく動いてしまうことがある」ということだ。
それをよしとするか、危険なことと見るかは、人によって異なるだろう。半藤氏は後者だ。半藤氏は、日本人が戦争から学ぶ一番大切な点は、「熱狂的になってはいけない」ことだ、と常に語っているそうだ。
熱狂的になっても碌なことはない、という教訓はよくわかる。しかし、覚めた分析や理性だけでは、人を動かすことも歴史を動かすこともできないだろう。理念やヴィジョンだけでは歴史は動かない。熱意と覚悟は必要である。熱意と熱狂は別物だが、世の中が大きく動く時代において、その違いを見抜くのは容易ではないように思える。
現代は熱狂の時代ではないと思う。また、熱狂を呼ぶような政治家の熱意も感じられない時代である。こんな時代に、歴史はどのようにして動くのだろうか。
本書で扱う時代はペリー来航の1853年から西南戦争の1877年までの24年間だ。西南戦争は明治10年なので、24年の内の10年は明治であり、この間の歴史を語るなら「幕末維新史」とする方が適切のように思える。
しかし、西南戦争までをあえて「幕末史」とした所に著者の史観がある。「維新」なんてフィクションだという見解である。
歴史は、それを語る人の立場によって様相が異なってくる。歴史上の人物の誰に肩入れして語るか、誰に共感しているかによって、歴史はいろいろな見え方をする。幕末期は主人公がはっきりしない群像の時代なので、共感する人物の違いによって情景が違って見える傾向が特に強いように思われる。
半藤氏がひいきにしているのは勝海舟である。明治32年まで生きた勝海舟は、多くの歴史座談を残している。晩年の勝海舟は、誰のことでもつい昨日会ったかのような調子で気さくに語ったそうだ。
幕末期に活躍した人物たちを、身近な知り合いとして生き生きと語る勝海舟のさまは、出版社の求めに応じて幕末史を歴史講談のように語る半藤氏に似ているところがある。
もちろん、著者は幕末を目撃しているわけではないが、二十数人の聴衆を前にした講義の縦横な語り口は魅力的である。話し言葉なので、登場人物も「阿部さん(阿部正弘)、堀田さん(堀田正睦)」、「わが愛する勝つぁん(勝海舟)」といった調子になる。あたかも目撃したかのような名調子になるのは、熟達の編集者の名人芸だ。
半藤氏が勝海舟を評価するのは、幕府や薩長という枠を超えた国のかたちが見えていた人物と見なしているからだ。半藤氏は次のように語っている。
「幕末にはずいぶんいろんな人が出てきますが、自分の藩がどうのといった意識や利害損得を超越して、日本国ということを大局的に見据えてきちんと事にあたったのは勝一人だったと私は思っています。」
西郷隆盛や坂本龍馬に新たな国家像を吹き込んだのは勝海舟であり、船中八策のオリジナルは勝海舟と大久保一翁にあると指摘している。
そんな勝海舟に共感する著者が語る幕末史のポイントは次の2点だ。
(1) 戊辰戦争は無駄で阿呆な戦争だった。薩長が天皇をうまく使って国家を乗っ取っただけの権力闘争・暴力革命だった。
(2) 戊辰戦争に勝利した薩長には、新たな国家の青写真も設計図もヴィジョンもなかった。
本書が西南戦争と大久保利通暗殺までを一区切りとしているのは、西南戦争のきっかけになった征韓論の論争を戊申戦争の権力闘争の継続だったと見なしているからだ。暴力革命の決着までを幕末史としているのだ。
戊申戦争を無駄で阿呆な戦争と見る視点は、その直前の大政奉還によって歴史はすでに大きく動いたと見なすことに通じる。
戊申戦争がなくても、この時期に日本は封建社会から近代社会へ転換したはずであり、その場合の新たな国家の姿は薩長が作った明治国家とは違った形になったに違いない……そんな思いが伝わってくる本である。
ヴィジョンなき薩長が作り上げたのは「維新」という言葉であり、皇国史観だった。戊申戦争がなければ、天皇制や天皇の位置づけも、その後の歴史とはかなり違った形になったはずだ。
戊辰戦争がなかったとすれば、徳川慶喜がその後の時代の主役を担った可能性が高いように思われるが、半藤氏は徳川慶喜にはあまり同情的ではない。それほど高く評価していないようだ。慶喜よりは家茂が好きだったと思われる勝海舟の目を通した評価なのかもしれない。
それはともかく、本書を読んであらためて感じたのは「理念やヴィジョンがなくても、ある種の熱気だけで世の中が大きく動いてしまうことがある」ということだ。
それをよしとするか、危険なことと見るかは、人によって異なるだろう。半藤氏は後者だ。半藤氏は、日本人が戦争から学ぶ一番大切な点は、「熱狂的になってはいけない」ことだ、と常に語っているそうだ。
熱狂的になっても碌なことはない、という教訓はよくわかる。しかし、覚めた分析や理性だけでは、人を動かすことも歴史を動かすこともできないだろう。理念やヴィジョンだけでは歴史は動かない。熱意と覚悟は必要である。熱意と熱狂は別物だが、世の中が大きく動く時代において、その違いを見抜くのは容易ではないように思える。
現代は熱狂の時代ではないと思う。また、熱狂を呼ぶような政治家の熱意も感じられない時代である。こんな時代に、歴史はどのようにして動くのだろうか。
理念なき過激派が歴史を動かした---薩長への怒りの書 ― 2011年06月23日
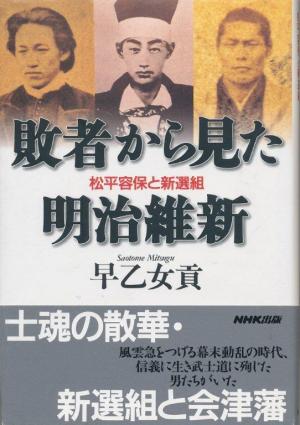
NHKの大河ドラマはほとんど観ていないが、数年前の「新選組」は観た。そのとき、新選組にハマって読んだ本の一つが『敗者から見た明治維新:松平容保と新撰組』(早乙女貢/NHK出版)だった。このたび、幕末史を振り返ってみようと思い、再読した。
会津藩士の末裔である早乙女貢氏の薩長への怒りが伝わってくる本だ。早乙女氏は、明治維新の真実は薩長の強権によって抹殺されたと主張する。薩長の立場で語られる幕末維新の様相をほぼ全否定し、会津藩から見た歴史こそが実相であるとした本書は、ある意味ではわかりやすい本である。
著者が評価するのは京都守護職だった会津藩主・松平容保であり、新選組である。最大の悪者は長州、次いで薩摩だ。徳川慶喜も非難の対象になっている。
私は本書を読んで、さほど極端な見解だとは思わなかった。会津藩からは、歴史がこのように見えるのは当然だと思う。共感できる部分も多い。
松平容保こそが純粋な勤皇で、薩長は天皇を利用しただけだという主張も間違っていない。
孝明天皇は松平容保を心の友と見ていたそうだが、その容保は薩長によって逆賊にされてしまう。蛤御門の変で天皇に大砲をぶっぱなした長州が勤皇で、鳥羽伏見の戦いで錦旗を見て刃を納めた会津や新選組が逆賊というのは、やはり、おかしな話だ。
会津藩は明治になってからも新政府から苛酷な仕打ちを受ける。これは、不条理な受難史ロマンのようでもある。
早乙女氏は明治の元勲たちを「元テロリスト」と指弾する。間違いではない。ただし、元テロリストが政治の中枢を掌握するのは珍しいことではない。それが「革命」の姿のひとつだろう。やはり、幕末は革命だったのだ。
早乙女氏は薩長だけでなく、徳川慶喜にも手厳しい。松平容保を裏切った小心で短慮で無責任な卑怯者としている。この評価は一方的で、徳川慶喜にはちょっと気の毒だと思う。本人は、そんなことを気にしないタイプの人だったかもしれないが。
本書では「勤皇攘夷」の欺瞞性も論じている。早乙女氏は、攘夷は一部の若者たちに蔓延した熱狂だとし、「人生を知らぬ若者には遠望が利かない。目前の事象だけで行動に走りたがるのだ」と、短慮な若者たちを批判している。
また、「勤皇攘夷」はお調子もののモダンボーイたちが振りまわす観念で、京都で「勤皇攘夷」を叫んでいれば、飯が食えて、酒や女にありつけたと述べている。「勤皇攘夷」を標榜して総会屋のような強請をする者もいたという。
もちろん、真面目に「勤皇攘夷」を追究している者もいただろうが、付和雷同するお調子ものが少なくなかっただろうことは、わが人生経験からも容易に想像できる。若者とは、そういう存在でもあるのだ。
また、早乙女氏は「薩長土肥勢力による徳川幕府の打倒には統一された理念はなく、場当たり的な行動の結果だった」としている。半藤一利氏と似た見解だ。
倒幕の理念はなかったとしても、ある種の恨み(復讐心)はあったかもしれない。早乙女氏が薩長を恨むのと同じように、幕末の長州は幕府に対して安政の大獄(彼らの師・吉田松陰が殺された)や長州征伐への恨みを抱いていたかもしれない。また、会津や新選組に対しては蛤御門の変や池田屋事件への仕返し気分があったかもしれない。
単に恨みや逆恨みを積み重ねても「理念」は出てこない。そんな要素を洗い流したあとに残る倒幕の必然性があれば、それが歴史を動かす理念だろうか。
早乙女氏は、薩長の「理念なき革命」が現代の諸悪の元凶だ、とまで主張している。次のような調子だ。
「長州人の野望が、近世日本の精神と文化を破壊し、人間性を堕し、救い難いほどの今日の退廃した社会の源流をなしたことは、政界の腐敗ぶり、社会不安を醸成する日々の残虐な少年犯罪などに歴然たるものがある。」
「この流血の明治維新が、どれだけ日本の美しい精神を打ち砕き、人間性を堕落せしめたか。会津藩に見る日新館教育の持つ道徳性、家族愛、武士道の純粋さとは、あまりに違いすぎた。」
坊主憎けりゃ…という気もするのだが。
いずれにしても、著者の思惑とは異なり、本書が図らずも明らかにしているのは、理念なき過激派でも(だからこそ)もつことができた「歴史を動かす力」の大きさである。
会津藩士の末裔である早乙女貢氏の薩長への怒りが伝わってくる本だ。早乙女氏は、明治維新の真実は薩長の強権によって抹殺されたと主張する。薩長の立場で語られる幕末維新の様相をほぼ全否定し、会津藩から見た歴史こそが実相であるとした本書は、ある意味ではわかりやすい本である。
著者が評価するのは京都守護職だった会津藩主・松平容保であり、新選組である。最大の悪者は長州、次いで薩摩だ。徳川慶喜も非難の対象になっている。
私は本書を読んで、さほど極端な見解だとは思わなかった。会津藩からは、歴史がこのように見えるのは当然だと思う。共感できる部分も多い。
松平容保こそが純粋な勤皇で、薩長は天皇を利用しただけだという主張も間違っていない。
孝明天皇は松平容保を心の友と見ていたそうだが、その容保は薩長によって逆賊にされてしまう。蛤御門の変で天皇に大砲をぶっぱなした長州が勤皇で、鳥羽伏見の戦いで錦旗を見て刃を納めた会津や新選組が逆賊というのは、やはり、おかしな話だ。
会津藩は明治になってからも新政府から苛酷な仕打ちを受ける。これは、不条理な受難史ロマンのようでもある。
早乙女氏は明治の元勲たちを「元テロリスト」と指弾する。間違いではない。ただし、元テロリストが政治の中枢を掌握するのは珍しいことではない。それが「革命」の姿のひとつだろう。やはり、幕末は革命だったのだ。
早乙女氏は薩長だけでなく、徳川慶喜にも手厳しい。松平容保を裏切った小心で短慮で無責任な卑怯者としている。この評価は一方的で、徳川慶喜にはちょっと気の毒だと思う。本人は、そんなことを気にしないタイプの人だったかもしれないが。
本書では「勤皇攘夷」の欺瞞性も論じている。早乙女氏は、攘夷は一部の若者たちに蔓延した熱狂だとし、「人生を知らぬ若者には遠望が利かない。目前の事象だけで行動に走りたがるのだ」と、短慮な若者たちを批判している。
また、「勤皇攘夷」はお調子もののモダンボーイたちが振りまわす観念で、京都で「勤皇攘夷」を叫んでいれば、飯が食えて、酒や女にありつけたと述べている。「勤皇攘夷」を標榜して総会屋のような強請をする者もいたという。
もちろん、真面目に「勤皇攘夷」を追究している者もいただろうが、付和雷同するお調子ものが少なくなかっただろうことは、わが人生経験からも容易に想像できる。若者とは、そういう存在でもあるのだ。
また、早乙女氏は「薩長土肥勢力による徳川幕府の打倒には統一された理念はなく、場当たり的な行動の結果だった」としている。半藤一利氏と似た見解だ。
倒幕の理念はなかったとしても、ある種の恨み(復讐心)はあったかもしれない。早乙女氏が薩長を恨むのと同じように、幕末の長州は幕府に対して安政の大獄(彼らの師・吉田松陰が殺された)や長州征伐への恨みを抱いていたかもしれない。また、会津や新選組に対しては蛤御門の変や池田屋事件への仕返し気分があったかもしれない。
単に恨みや逆恨みを積み重ねても「理念」は出てこない。そんな要素を洗い流したあとに残る倒幕の必然性があれば、それが歴史を動かす理念だろうか。
早乙女氏は、薩長の「理念なき革命」が現代の諸悪の元凶だ、とまで主張している。次のような調子だ。
「長州人の野望が、近世日本の精神と文化を破壊し、人間性を堕し、救い難いほどの今日の退廃した社会の源流をなしたことは、政界の腐敗ぶり、社会不安を醸成する日々の残虐な少年犯罪などに歴然たるものがある。」
「この流血の明治維新が、どれだけ日本の美しい精神を打ち砕き、人間性を堕落せしめたか。会津藩に見る日新館教育の持つ道徳性、家族愛、武士道の純粋さとは、あまりに違いすぎた。」
坊主憎けりゃ…という気もするのだが。
いずれにしても、著者の思惑とは異なり、本書が図らずも明らかにしているのは、理念なき過激派でも(だからこそ)もつことができた「歴史を動かす力」の大きさである。




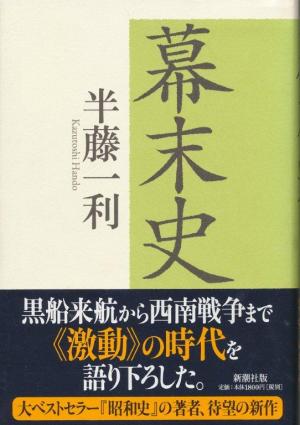
最近のコメント